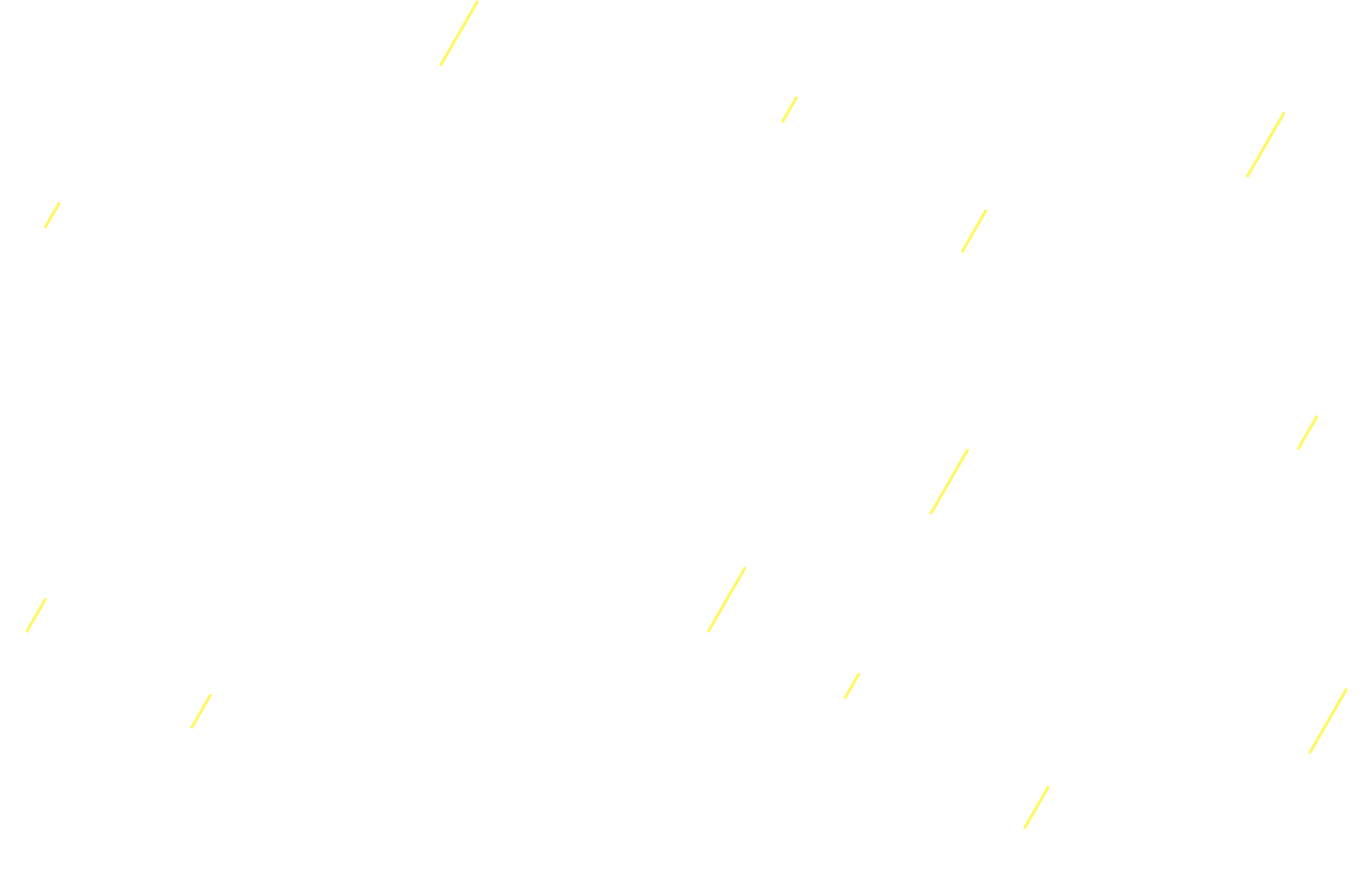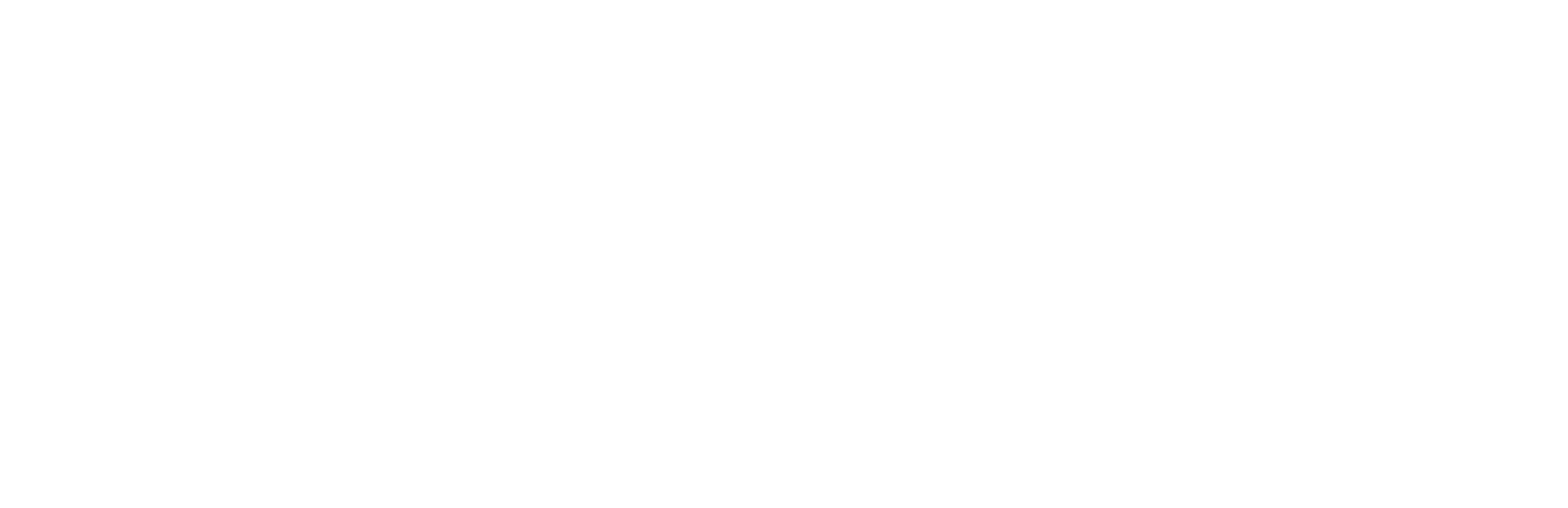「あれもこれも」から脱却!中途半端な採用活動から抜け出すための課題抽出法とは
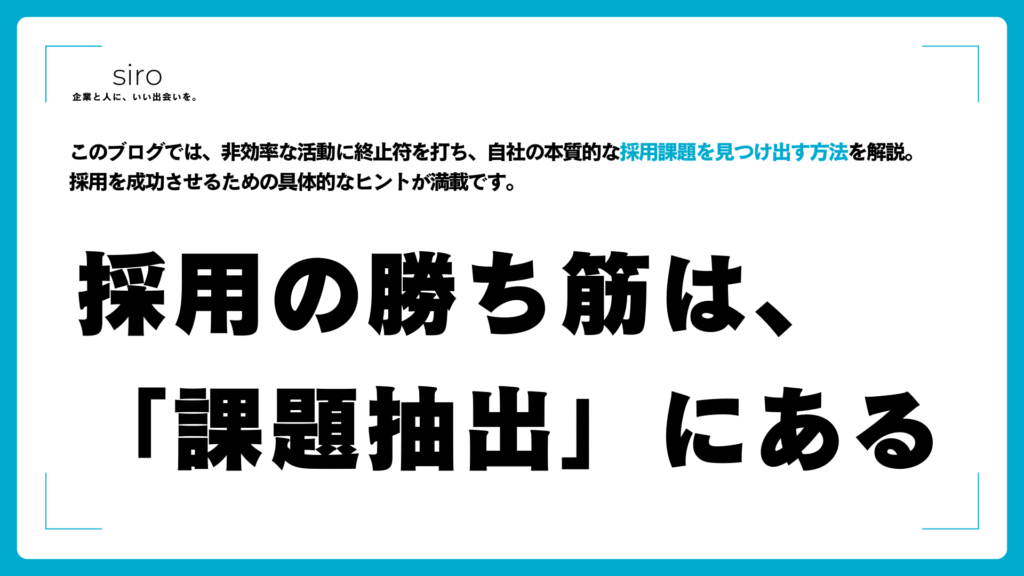
「新しい採用手法を次々に試しているのに、なぜか手応えがない」
「時間もコストもかけているのに、理想の人材になかなか出会えない」
もし、このような悩みを抱えているなら、それは施策の数が足りないのではなく、取り組むべきことの優先順位が明確になっていないからかもしれません。
採用活動において最も重要なのは、新しい施策に手当たり次第に飛びつくことではなく、まず自社が抱える本当の課題は何かを正確に把握することです。
この記事では、多くの企業が陥りがちな「あれもこれも」状態から抜け出し、採用活動の方向性を明確にして成果に繋げるための「課題抽出」の方法を具体的に解説します。
なぜ「採用課題の抽出」が最重要なのか?
根本的な課題を放置したまま新しい施策に投資をしても、時間やコストといった貴重なリソースが効果的に使われず、無駄になってしまう恐れがあります。
「採用課題の抽出」とは、自社の採用活動全体を客観的に分析し、問題点を正確に特定するプロセスです。まずどこに問題があるのかをはっきりとさせることで、初めて的確で効果的な解決策を立てることができるのです。
課題抽出がもたらすメリットは明確です。
- リソースの最適化: 最も効果的なポイントに人、モノ、コスト、時間を集中投下できる。
- 戦略の明確化: チーム内で「何をすべきか」の共通認識が生まれ、施策に一貫性が生まれる。
- 採用の質的向上: 自社に本当にマッチした人材を見極め、的確に惹きつけられるようになる。
まずは一度立ち止まり、自社の現状を正しく見つめ直すこと。それが、成果への最短ルートです。
要注意!採用活動で「あれもこれも」状態に繋がる4つの落とし穴
なぜ多くの企業が、非効率だと分かっていながら「あれもこれも」状態に陥ってしまうのでしょうか。そこには、いくつかの典型的な落とし穴があります。
1:流行への追随
「とりあえずSNS」「うちもリファラル採用を」など、他社の成功事例やトレンドに乗り遅れまいと、目的が曖昧なまま新しい手法に手を出してしまうケースです。
2:手段の目的化
採用イベントへの出展や、新しい採用管理ツール(ATS)の導入そのものが目的になっていませんか?それらはあくまで課題解決の「手段」であり、導入自体がゴールではありません。
3:部分最適の積み重ね
経営層は「即戦力」、現場は「カルチャーフィット」、採用担当は「採用人数」。それぞれが良かれと思って動いた結果、施策が噛み合わず、候補者を混乱させ、全体の力が分散してしまうという落とし穴です。
4:「課題特定」のスキップ
これが最も根深く、本質的な落とし穴です。現状分析や課題の深掘り(Why)を怠り、「どうやるか(How)」という解決策にすぐに飛びついてしまう。原因が分からないまま対症療法を繰り返しても、根本的な解決には至りません。
心当たりがあると感じたら、それは採用戦略を見直す絶好の機会です。
自社の「本当の採用課題」を掘り起こす5ステップ
では、具体的にどうすれば自社の課題を掘り起こせるのでしょうか。
1.数値で現状を「見える化」する
まずは客観的なデータと向き合いましょう。応募数、書類通過率、面接通過率、内定承諾率といったファネルごとの数値や、媒体別の費用対効果を洗い出します。どこで候補者が最も離脱しているのか、ボトルネックを数字で正確に把握することが第一歩です。
2.関係者の「生の声」に耳を傾ける
数値だけでは見えない「質」の課題を浮き彫りにします。経営層、現場社員、面接官、そして可能であれば内定辞退者や新入社員にヒアリングを行いましょう。「どんな人と働きたいか」「入社の決め手は何か」「なぜ辞退したのか」といった生の声に、課題解決の重要なヒントが隠されています。
3.採用プロセスを「候補者目線」で可視化する
候補者が自社を認知してから入社するまでの過程を候補者の視点で見直し、すべての接点を洗い出します。求人票の文面、スカウトメール、面接官の態度、オフィスの雰囲気など、各ポイントで候補者は何を感じているでしょうか。その過程が魅力的で、一貫性のあるものになっているかを確認します。
4.市場と競合を分析し「自社の立ち位置」を知る
採用は、市場にいる候補者を競合他社と取り合う競争です。競合はどのような条件や魅力を提示しているのか、市場のトレンドはどうなっているのか。外部環境を分析することで、初めて自社の相対的な強みと弱みが明確になり、効果的なアピール方法が見えてきます。
5.すべてを統合し「本質的な課題」を特定する
最後に、集めた定量データ、定性的な声、プロセスの問題点、市場環境をすべて突き合わせます。「なぜ内定辞退が多いのか?」という事象に対し、「面接での魅力付けが弱いから」であり、その背景には「現場が求める人物像と、採用担当がアピールしている内容にズレがあるから」といったように、表面的な問題の裏にある根本原因を突き止めます。
抽出した課題にどう向き合うか?~「あれもこれも」からの卒業~
課題が特定できたら、いよいよ卒業の時です。しかし、焦ってすべての課題に手を出してはいけません。ここでも「あれもこれも」に戻ってしまっては本末転倒です。
1.「やらないこと」を決める
リソースは有限です。まずは効果の薄い施策、優先度の低い取り組みをやめる勇気を持ちましょう。何かを「始める」ことより、何かを「やめる」ことの方が難しいですが、これこそが集中力を生むための重要なステップです。
2.インパクトと実現性で優先順位をつける
抽出した課題を「解決した時の効果の大きさ(インパクト)」と「取り組みやすさ(実現性)」の2軸で整理し、最も費用対効果の高いものから着手します。
3.具体的なアクションプランに落とし込む
「魅力付けを強化する」といった曖昧な目標ではなく、「誰が・いつまでに・何をやるか」を具体的に設定します。「採用担当のAさんが、6月末までに、社員インタビュー記事を3本作成しサイトに掲載する」というレベルまで落とし込み、行動を明確にしましょう。
まとめ|中途半端な採用活動から抜け出し、成果を出すためには
採用活動が迷走していると感じたら、施策の数を増やす前に、まずは一度立ち止まることが重要です。
データと向き合い、社内の声に耳を傾け、自社の現在地を正確に知る。「採用課題の抽出」とは、単なる問題点の洗い出しではありません。それは、自社の提供価値や働くことの魅力を再発見し、未来の仲間へと届けるための言葉を磨き上げるプロセスです。
正しい課題認識に基づいた一貫性のある採用活動は、採用の成功だけでなく、企業全体のブランディング強化にも繋がります。
私たち株式会社siroでは、クリエイティブとマーケティングの視点から、企業様の事業や採用における本質的な課題を抽出し、解決までを伴走支援します。
「自社だけでは客観的な分析が難しい」「課題は分かったが、具体的な解決策に落とし込めない」といったお悩みをお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
siro編集部
siro編集部は株式会社siroのメンバーによって構成されるコンテンツ制作チームです。企業のHR領域に関するお役立ちブログやセミナー情報またケーススタディ、その他siroのカルチャーなどをお届けします。