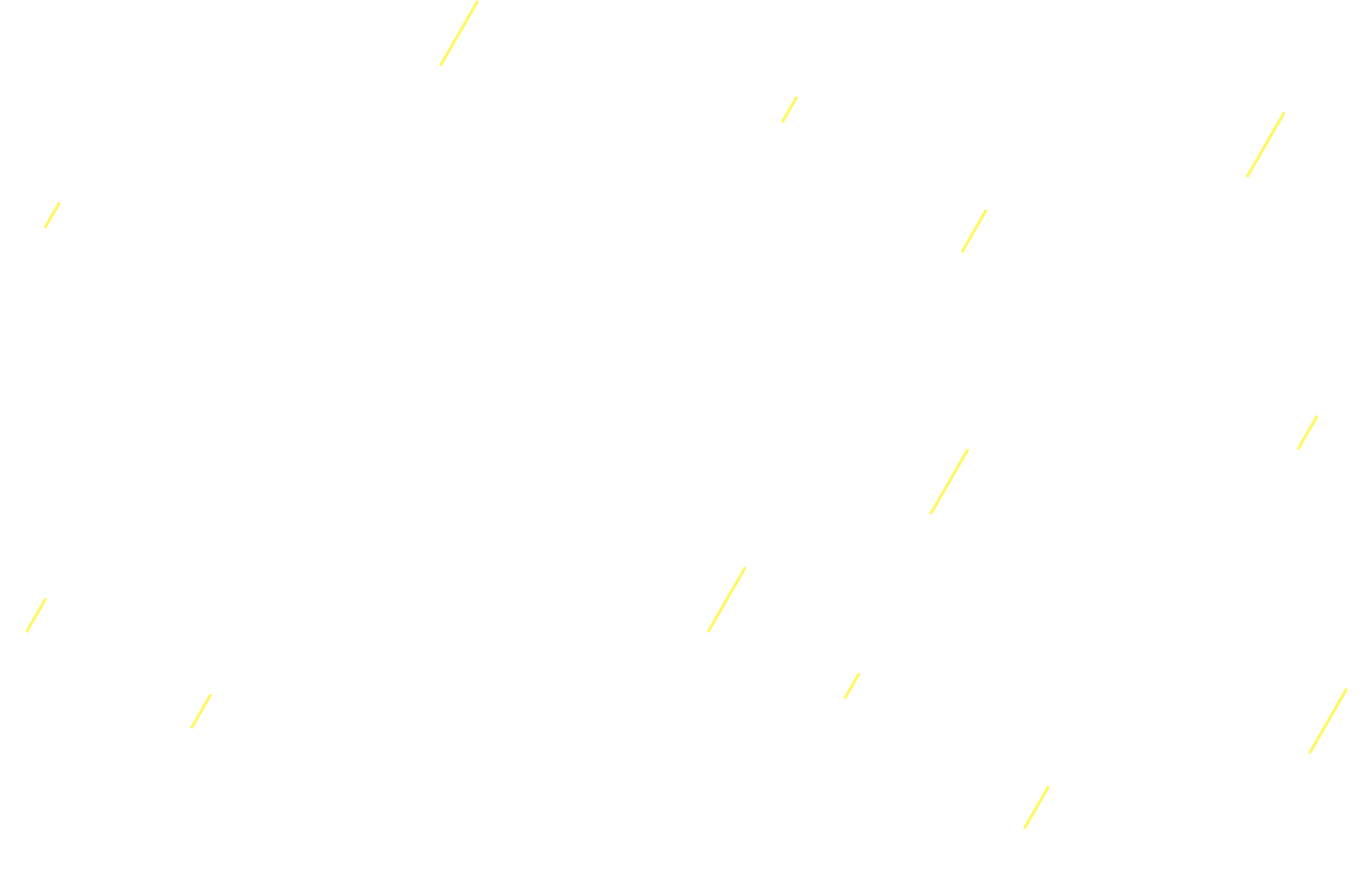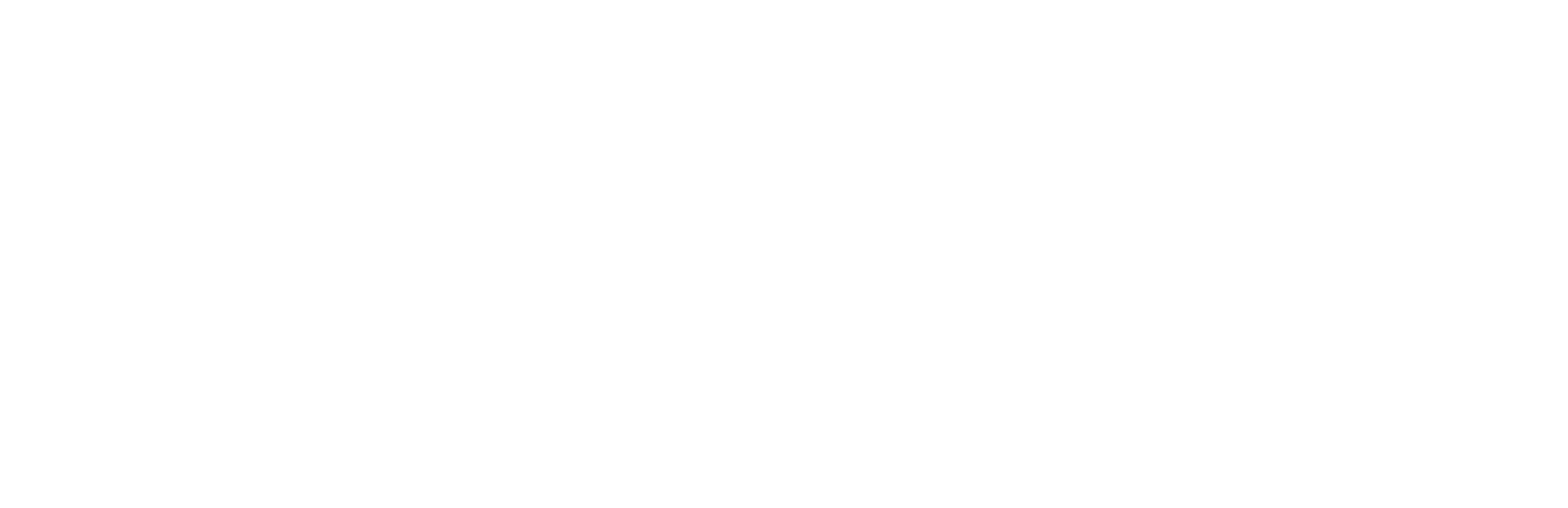採用難を乗り越える2つのキーワード「オフボーディング」と「アルムナイ採用」
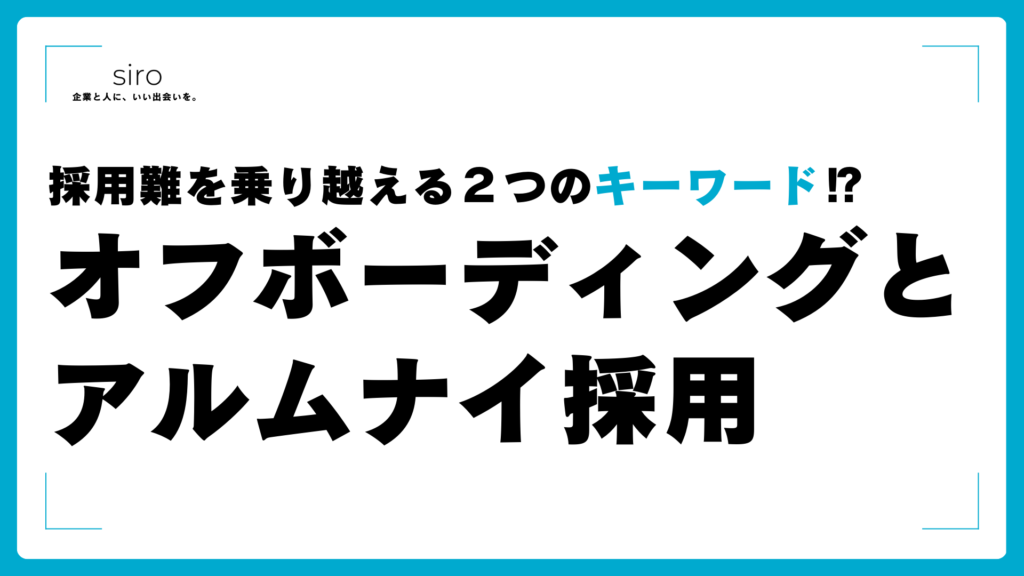
この記事お読みの皆さんは、きっと採用難を肌で感じていらっしゃるのではないでしょうか?
それもそのはず。採用難易度の指標となる「有効求人倍率」が1.0倍を最後に下回った(求人のほうが求職者より多かった)のは、2013年。それ以来、コロナ禍の最中を含めて一度も、1.0倍を割り込んでいません。
つまり「採用難」と言われる時代になってからもう12年が経過したということです。
そのような中、採用難を乗り越える策として「オフボーディング」と「アルムナイ採用」という2つのキーワードが注目されています。
耳慣れない言葉ですよね。しっかりと解説します!
気持ちよく辞めてもらう「オフボーディング」

オフボーディングという言葉から、「オンボーディング」を連想された方も多いかもしれません。
新しく入社した方に、社内システムの使い方や備品の保管場所を教えたり、新しく一緒に仕事をすることになる仲間を紹介したりして、新たな船(会社)でスムーズにオンボード(乗り込み)ができるように手助けする取り組みのことです。
オフボーディングはまさにその逆。自社を辞めていく方に向け、スムーズに船(会社)をオフボードする(降りる)手助けをする取り組みのことを言います。
オフボーディングは具体的に何をする?
もちろんオフボーディングの中には離職票や源泉徴収票の発行など事務手続きも含まれますが、採用難対策としての「オフボーディング」を行う場合には、さらに幅広いサポートを提供することが一般的です。
まず、ほとんどの企業で行われているのが人事や上司との面談。
面談とはいっても、離職することを責めたり、無理に慰留したりは決してしません。
引き継ぎの状況を確認し、退職までに必要なサポートについて尋ねて会社側が積極的に協力する姿勢を見せる事が一般的です。
たとえば、そこには新たなキャリア形成のためのサポートも含まれる場合もあります。
離職者が次の職場を決めていなければキャリアアドバイザーとの面談をセッティングしたり、次の職場が決まっているなら上司が推薦状や紹介状を書いてあげたりする例もあるようです。
他にも、新たな職場で困りごとがあったときに気兼ねなく相談ができるための窓口を社内に設けて紹介したり、希望があれば今後も社内イベントに参加できるようメールアドレスを残しておいたりと、オフボーディングに取り組む企業によって提供しているサポートは様々です。
オフボーディングが採用難に効く理由とは?
「辞めていく社員になぜそこまでしなくてはならないのか」と考える方もいるでしょう。経営者や人事担当者としては当然の感情です。
しかし考えてみてください。
雰囲気も最高で、料理も美味しい素晴らしいレストランで食事をしたとします。しかし会計のときにお釣りを投げ渡されたり、さっさと退店するように強く促されたりしたらどうでしょうか?
「終わりよければすべてよし」の逆、「終わりが最悪なら全てが最悪」になってしまいます。もう二度と、そのレストランに行くことはないでしょう。
会社も同じです。
離職のときに嫌な思いをしてしまった社員は、あなたの会社に対して悪い印象をもったまま、残りのキャリアを過ごすことになります。
そしてもう二度と、社員として戻ってくることはありません。ここがポイントです。
つまり、オフボーディングとは「離職した社員がまた自社に戻ってきてくれることを期待して」行う取り組みなのです。
卒業生を意味する「アルムナイ」 採用とどう関係が?

ではここで、次のキーワード「アルムナイ採用」についての解説に移ります。
アルムナイ(Alumni)は、主に「卒業生」を意味する英単語ですが、「離職者」を指す場合にも使うことができます。
つまり、「アルムナイ採用」とは離職者を再雇用する採用施策のことです。「出戻り採用」と言い換えると分かりやすいかもしれません。
とはいっても、定年退職者を嘱託やパートタイムとして再雇用する採用手法とは分けて考えることがほとんどです。多くの場合、まだまだ働き盛りで、新たなキャリアを求めて離職していった社員をもう一度、自社の社員として迎えることを指します。
アルムナイ採用にはどんなメリットが?
「辞めていった社員を採用することに何のメリットがあるのか」と考える方もいるでしょう。これも、経営者や人事担当者としては当然の感情です。
しかし、少なくとも一度は自社の採用試験を通過した人材は、自社が求める能力を持っていることが約束されています。
この人手不足の時代に、きわめて貴重な人材と言えるのではないでしょうか。
また自社とのマッチングだけでなく「問題点」が分かっていることも大きなメリットです。
一般の採用面接ではなかなか見えてこない、一緒に仕事をしたことがあるからこそ分かる問題点も把握した上で配置や役職を検討できる機会は、アルムナイ採用以外ではほとんどありえません。
つまり、アルムナイ採用のメリットは「良い面も悪い面も知っている人材を採用できる」ことにあります。通常の採用経路では決して出会えない人材なのです。
アルムナイ採用、具体的にどう進める?
では、ここまで読んでアルムナイ採用に興味を持たれた方に向けて具体的に採用活動を行うステップをご紹介します。
ざっくり、以下の3ステップです。
- 離職の際にはオフボーディングで「気持ちよく辞めてもらう」
- 離職後もリレーションを保ち続けて「いい関係を続ける」
- 元社員が希望したら面接を行い「採用可否・配置を考える」
1つずつ解説します。
アルムナイ採用のステップ1「気持ちよく辞めてもらう」
記事の前半でご紹介した「オフボーディング」の考え方で、自社に感謝した状態で離職してもらうことが理想です。人には「返報性の原理」というものがあり、「良くしてもらったら、何かを返したい」という基本的な欲求があります。
そうすることで、離職後も自社とのリレーションを維持するモチベーションを持ってもらうことができます。
アルムナイ採用のステップ2「いい関係を続ける」
いくら感謝の念を持って離職したとしても、時が経てば忘れられてしまうものです。つまり、離職した社員が、いつか次の職場も辞めて転職先を考えるときに自社に戻ってくるという選択肢も候補に挙げてもらうためには、何よりも「忘れられないこと」が重要になります。
具体的な方法は会社によってそれぞれですが、次のような方法をとる場合が多いようです。
- オンライン社内報を定期的にメールで送る
- バーベキューなどカジュアルな社内イベントに定期的に招待する
- とくに親しかった同僚や先輩などから定期的に連絡をとってもらう
- 1年、3年、5年といった「離職しやすい」タイミングで定期的に連絡をする
どれも大きな労力をかけることなく実施できる簡単な方法で、中小企業から大企業まで多くが採用しています。
アルムナイ採用のステップ3「採用可否・配置を考える」
いい関係を続ける努力が実り、離職した社員から再雇用の打診があったときに重要なのが、必ず採用試験を行って配置も再検討することです。
もともと一緒に仕事をしていた仲間なので、連絡があればすぐに採用したいと考えてしまうかもしれませんが、必ず一度は面接などの採用試験を行いましょう。
そうすることで、新たなキャリアの中で獲得したスキルを知ることができたり、逆にパーソナリティやスキルにマイナスの変化があったことを知ることができたりします。
また、当然ですが年齢は上がっています。それにともなってライフステージが変化したり、求める給与水準が上がっていたりするかもしれません。
それらの変化を確認し、自社で再雇用可能かどうかしっかりと検討することでアルムナイ採用は成功に繋がります。
アルムナイ採用のデメリットと対策

ここまでの解説で分かるように、経営者や採用担当者にとってアルムナイ採用は人手不足を解消する非常に魅力的な施策の1つです。
しかし、デメリットも存在します。
アルムナイ採用のデメリット:既存社員のモチベーション低下
離職した社員を再雇用すると、既存社員のモチベーションが下がってしまうことがあります。
よくある例は以下の3つです。
人間関係のトラブル:現場にヒアリングして解決
アルムナイ採用を行うと、経営者や人事担当者からは見えていなかった社員同士の人間関係に起因するトラブルが起こることがあります。
ひらたく言えば、既存社員から「嫌いだったアイツが戻ってくる」と受け止められてしまうことがあるということです。
場合によっては、経営者や人事担当者からは見えていなかった人間関係の問題を「再燃」させてしまうケースもあります。
アルムナイ採用を行う際には現場にも再雇用を打診し、その雇用がトラブルの元にならないか慎重に確認しましょう。
場合によっては配置を再検討したり、再雇用をしないという判断も重要です。
待遇の違いによる不公平感:評価制度を見直して解決
アルムナイ採用で再雇用する社員は、離職中に年齢だけでなくキャリアや経験も積んでいます。
また、採用市場の環境も刻々と変化しているため、再雇用の際に在籍時よりも高いオファーを出すこともあるでしょう。
すると、自社でずっと働いてきた既存社員からは「私はここで地道に頑張っているのに、一度辞めた社員が私よりも高く評価されるのは我慢できない」と不公平感を抱いてしまうことがあります。
評価制度の透明性を高め、雇用条件について現場で不公平感が生まれない仕組み作りが必要です。
既存社員の昇進が遅れる:採用理由を現場に開示して解決
さらに、アルムナイ採用の社員を役職者として雇用する場合、既存社員から見ると「限られたポストを、一度辞めた社員に奪われた」と感じてしまうことがあります。
採用を決めた理由を現場にもきちんと説明し、アルムナイ採用する社員がそのポストにふわさしいと判断した理由を納得してもらうことが重要です。
アルムナイ採用のデメリット:離職率が上がることがある
また、アルムナイ採用を活発に行うことで「いつでも戻ってこられる」という印象を既存社員に与えてしまい、離職率が上がるというケースもあります。
再雇用の理由を社内にきちんと周知することで「ただ辞めて戻ってきただけではなく、外でしっかり経験を積んできたから再雇用されたのだ」ということを社員に知ってもらうことで、安易な離職を防ぐことができます。
人手不足には「オフボーディング」と「アルムナイ採用」
「募集を出しても人が集まらない」「やっと集めた人材も面接をすると採用水準に達していないことが多い」など、人手不足の時代に多くのお悩みを抱えていらっしゃると思います。
そのお悩みを解決する一手が「オフボーディング」と「アルムナイ採用」です。
自社の風土、文化、業務内容をしっかりと理解し、一度は採用試験を通っているのでスキル面でも信頼のおける人材は、アルムナイ採用以外の方法で出会うことができません。
一方、自社を辞めてからのキャリアでどのような変化があったのかしっかりと確認し、既存社員にも気を配りながら、再雇用可能か慎重に検討することもまた重要であることは忘れないようにしてください。
この記事が、みなさまの採用課題の解決に繋がることを願っています!
Yuta Tsukaoka
コンテンツプロデューサー。スタートアップからナショナルクライアントまで幅広い企業に対し、コンテンツマーケティングによる課題解決の支援を提供している。 趣味は熱帯魚・園芸・車中泊旅行。